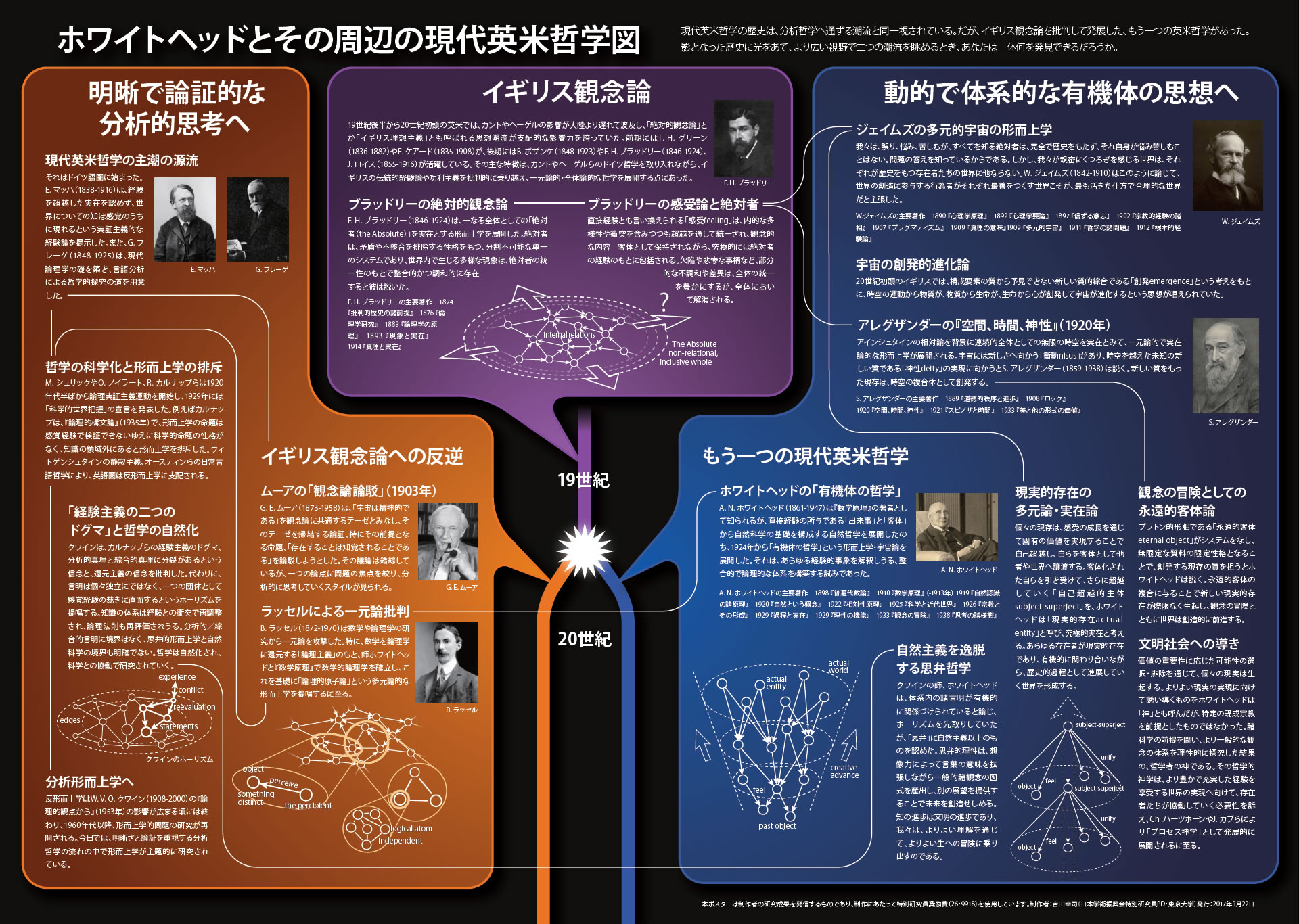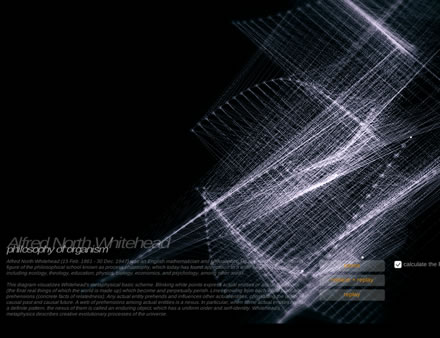有機体論の萌芽
「出来事と客体」のページでは、出来事は、時空的で、諸部分へと分割可能であるのに対して、客体は、直接的には時空のうちになく、部分へと分割不可能であることをみました。しかし、「有機体」とは、諸部分の構成成分をもちながらも、部分と全体が本質的に統一されているという意味で「分割不可能(individual)」なものです。そのため、「有機体」という概念を考える上で、「出来事」と「客体」は対立してしまいますが、逆にいえば、それらを結びつけることができれば、ホワイトヘッドの「有機体の哲学」の萌芽が形成されます。このページでは、中期自然哲学に見出せる、ホワイトヘッドの有機体論の形成について解説します。
|
自己同一的なパターンと唯物論的機械論
|
|
| 「出来事と客体」のページでみた通り、出来事は直接的に時間や空間のうちにあり、諸部分に分割できます。一方で、客体は直接的には時間や空間のうちになく、部分への分割性をもちません。ホワイトヘッドによれば、客体は「(厳密に言うと)時間や空間なしに存在する」。 | |
| しかし、ホワイトヘッドは、このように言う一方で、「客体は諸出来事に対する関係性のゆえに時間や空間のうちに派生的にあるに過ぎない」とも言っています。このことは裏を返していえば、たとえ派生的であるに過ぎないにしても、客体は出来事に対する関係性のゆえに時間や空間のうちにあるともいえるでしょう。出来事と客体は一見、相対立するようですが、実際には互いに他を必要とし関係づけられています。客体は出来事の性格(character)であるがゆえに、間接的に時間や空間のうちにあり、部分‐全体関係に関わっているのです。『自然認識の諸原理』でホワイトヘッドはそれを「パターン(pattern)」を含む客体と呼びます。例えば、金太郎飴を想像してみてください。金太郎飴のどの部分を切っても、同じ絵柄が出てきます。各断面に現れる同じ絵柄を自己同一的な「客体」と考えましょう。もしここで、金太郎飴を出来事と考えるならば、その絵柄は、どれも異なる絵柄です。ある断面A、別の断面B、さらに別の断面Cは、どれも異なる出来事です。出来事である限り、金太郎飴は、諸部分に分割することできます。しかし、それらの出来事は、同じパターン(絵柄)を「反復」しています。AもBもCも、あくまで出来事であるにもかかわらず、同じ絵柄がパターンとして繰り返されている。では、この繰り返されているものは何かといえば、絵柄、つまり「客体」です。一般に、客体は部分‐全体関係をもたないのですが、パターンと呼ばれる客体は、諸出来事の中で、繰り返し現れます。そして、繰り返し現れるということによって、パターンという客体は、間接的に、部分―全体関係をもっているような客体と考えることもできます。 | |
| 生成する自然の過程は、パターンを反復することによって自己同一性を保持し、「存続する客体(enduring object)」であると考えられます。ある一つの出来事のうちに現れているパターンが、その出来事の諸部分においても反復して現れるということが「存続(endurance)」です。パターンが、継起する諸部分を通じて反復され、全体においてそのパターンが示されているとき、その出来事は、単に生成するのではなく、「存続している」と言われます。 | |
| パターンは、全体における部分の反復、あるいは逆に、部分の反復による全体の構成を説明する用語ではあります。しかし、それは、多を統一する個体性(individuality)や、部分と全体の不可分性を説明する用語ではありません。全体が諸部分によって構成される限りで、パターンはむしろ、ホワイトヘッドが批判する「唯物論的機械論(materialistic mechanism)」の説明原理となるべき概念です。ホワイトヘッドのいう唯物論的機械論とは、全体は、単なる部分の集合として、本質的に部分に影響することがないという考えです。例えば、たくさんの部品からなるロボットを考えてみましょう。それは、部品という諸部分から、全体が構成されています。しかし、どの部品も壊れれば他の部品に取り換えることできます。この意味では、どの部品も、ロボット全体にとって、かけがえのないものではなく、交換可能なものです。人間の脳は、他の人の脳と取り換えると、その人ではなくなるという点で、その人(全体)と脳(部分)が、かけがえのないものとして本質的に結びついています。他の器官も、臓器移植すると拒絶反応が生じる点では、全体に対して、かけがえのない本質的な関係をもつものです。機械や物質の場合、そうではありません。物質は、諸要素の相互の連関を欠いたまま、あるとき・ある場所に位置を占めることができます。ホワイトヘッドは、これを「単に位置を占めること(simple location)」といいます。それぞれの物質は、自然法則で表現される全体のプランのうちで、決められた経路を主体性なく運動すると考えられます。ここに、合目的性や価値の実現といった有機的な連関が入り込む余地はありません。全体が部分によって、部分が全体によって説明し尽くされるパターンとは、むしろ唯物論的機械論を説明する概念なのです。 | |
| では、ホワイトヘッドの有機体論の着想は中期哲学のどこにあったのかと問うとき、その萌芽は、『自然認識の諸原理』の「リズム」の章における「生きている客体(living object)」に見出せます。この客体は、自らのうちにパターンの反復を含み、ある程度は自己同一的です。しかし、それは、単なるパターンの反復ではなく「生命的なものを含んでいる客体」として理解されています。ホワイトヘッドは、「リズムの表現やリズムに対する感受性を保持している。生命とはそのようなものとして理解されるリズムなのである」と言います。 | |
| この客体がもつ「生命らしさ(liveliness)」は、その客体の状況である出来事との関係性によって認識されます。すなわち、自然には、出来事と、その出来事のうちに示されるパターンとの「コントラスト(contrast)」があります。一方で、生成する出来事は「推移」という性格によって「生命(life)」に「新しさ(novelty)」を与えます。他方、パターンは生命に「同一性(identity)」を与えます。これら新しさと同一性が相俟って「リズム」を構成します。ホワイトヘッドによれば、「リズムの本質とは同一性と新しさの融合である。その結果、諸部分が、その細部の新しさから生じているコントラストを表示している一方で、全体はパターンの本質的統一を失うことはない」。かくして自然には「創造的前進」があり、「自然は生命を含むのである」。 | |
| 一見、机や椅子といった「物理的客体」は、「現象的性格」、つまり、私たちの知覚に現れている物質的客体として「一様(uniform)」です。机や椅子といった、物質的存在に、リズムなんてものはないように見えます。ところが、「原因的性格」に注目するとき、それらは、一様ではないリズムの性格をもっています。どういうことかといえば、自然の原因的性格が細分化されていくことによって明らかとなる原子や分子といった「科学的客体」と、その状況の出来事である「場」とには、リズムがあるということです。例えば、一つの楽曲は、一つ一つの音符に分解してしまったら、メロディーもリズムも失われてしまいます。一つ一つの楽音ですら、ある一定の波長をもち、その振動周期よりも短い期間には存在しえません。一つ一つの音は、ある一定の持続のうちで全体として知覚されるのです。同様に、原子や分子も、一定の波長をもちます。ゾンマーフェルトの量子条件を考えてみれば、ある原子が安定して存続するのは、量子条件を満たすときです。そうでないときは、原子は、エネルギーを減衰して、崩壊してしまいます。原子や分子は、機能するために必要な周期性があり、この意味でリズムある存在だといえます。そして、机や椅子も、「原因的性格」を探究すれば、原子や分子にたどり着くのですから、つまるところ、リズムある存在だと考えられるのです。 | |
| 生命、あるいはリズムとしての客体は、「非一様な客体」と呼ばれます。「非一様な客体」は、部分と全体が本質的に不可分で、ある一定の持続をもった統一的な全体としてのみ現実に存在します。そのため、単に機械論的な存在ではなく、有機体としての存在です。中期哲学において出来事と客体は対照的でしたが、この客体は、絶え間なく進展する出来事の生成と、恒久的な客体の自己同一性とを兼ね備えています。それは、コントラストというかたちで差異性を孕みながら、パターンの反復によって同一性も保持し、諸部分を本質的に統一した全体として現実に存在するのです。 | |
| 中期哲学のリズムや生命という概念は、ホワイトヘッドの後期哲学では、表立ってはあまり使われなくなります。ですが、考え方自体は、『科学と近代世界』の出来事という概念にも引き継がれています。「有機体の哲学」と呼ばれる哲学は、中期自然哲学のリズム論、生命論で既に形成されつつあったのです。後期哲学における有機体論の発展は、『科学と近代世界』のページで詳しくみていきましょう。 |