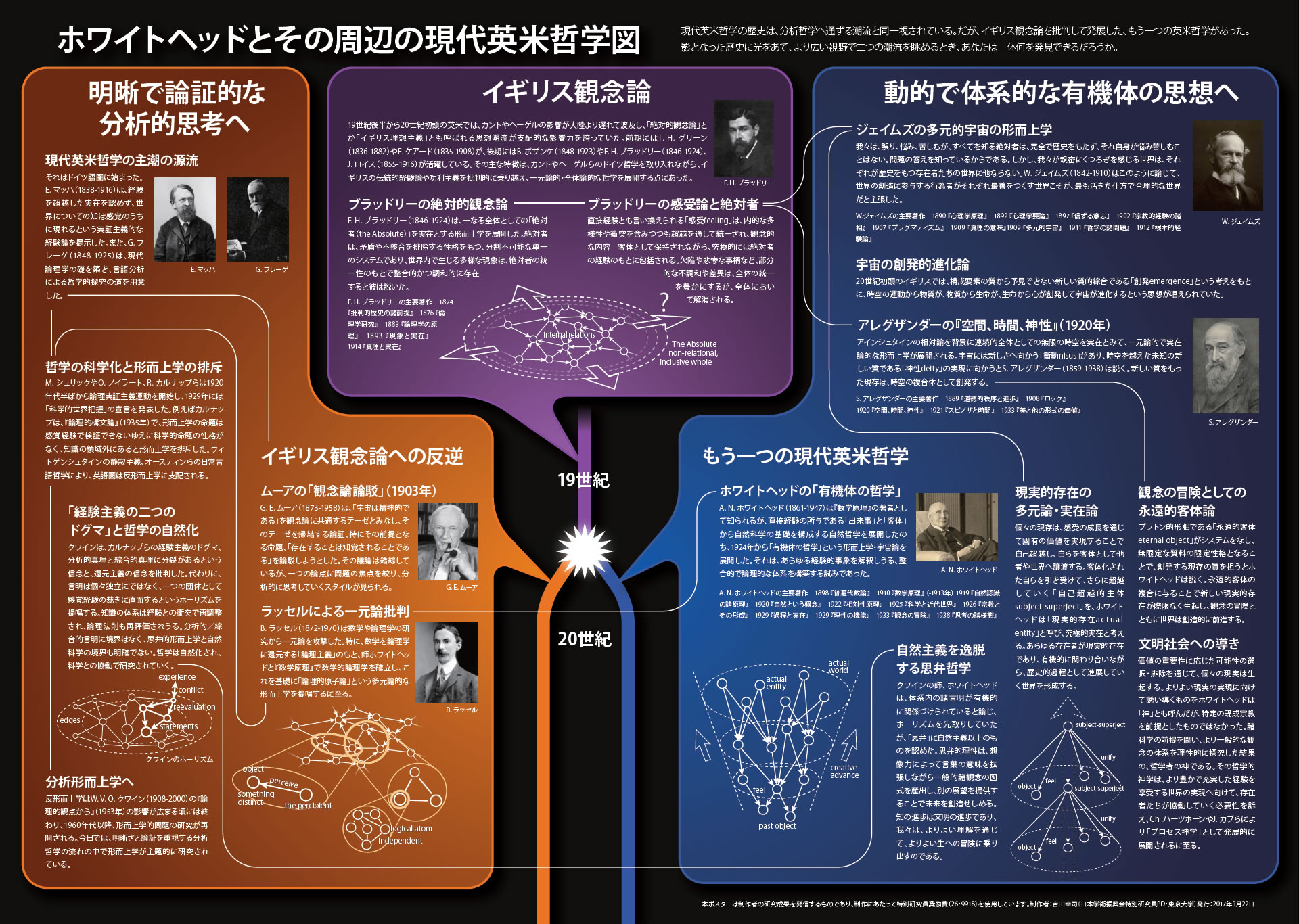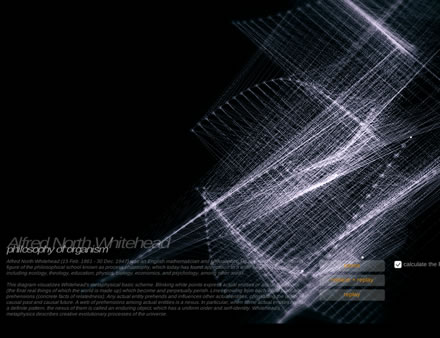現実的生起と結合体の発展史的起源
『科学と近代世界』のうちローウェル講義をもとにした箇所でホワイトヘッドは自らの有機体論には「数学や数理物理学に関する私自身の研究によって」(SMW 152)到達したと述べています。また、『過程と実在』の第III部「抱握の理論」は、単純な物的抱握から始まり、人間のような高次の有機体がもつ経験の高度な諸相は後半部で論じられる構成になっています。これらはホワイトヘッドが発生論的に低次の有機体から高次の有機体へ向けて考究していたことを示唆しています。実際、第3章で考察した通り、ローウェル講義の形而上学は、自然科学の基礎づけという課題の中で形成されたと考えられます。
しかし一方で、あとで加えられた『科学と近代世界』の「抽象」の章では、記述的である形而上学的分析の正当化は「我々の直接経験を構成する現実的生起に関する我々の直接的知識」(SMW 158)に求められるべきだとも述べられています。また、『過程と実在』でも次のように書かれています。
実現されているにせよいないにせよ、現実的生起の力能を記述するにあたって、我々はロックとともに、形而上学に要求される一般化された記述を基礎づける一例として、人間経験を暗黙のうちに取り上げてきた。しかし、より低次の有機体に目を向ける時、我々の基準である人間経験と比較して最初に決定しなければならないのは、これらの能力のいずれが、実現から関連のない状態へと消えていくか、ということである。(PR 112)
これらの箇所は、ホワイトヘッドがまず人間経験を範例にし、そこから種々の機能を差し引いていくことによって、心的極が極微であるような低次の有機体へと分析していったことを暗示しています。前節でみた通り特にローウェル講義では、反省を伴う認識は高次の有機体のうちにみられていたのであり、ローウェル講義から『科学と近代世界』刊行に至るまでの間についてはこの方向性を想定して諸段階を跡づけることができるのではないでしょうか。
しかも1925年ハーヴァード講義では「(現実的)生起」という術語や、結合体の発想も登場していることから、主体概念の捉え直しは、ホワイトヘッド哲学における最も基本的な考えである現実的生起や結合体の由来にも密接に関わっていると思われます。そこで本節では、『科学と近代世界』でホワイトヘッドが主体(性)をどのように体系内に位置づけていったのかを順に追っていくことを通して、現実的生起や結合体の由来を究明していきます。
|
―ローウェル講義から『科学と近代世界』刊行に至るまでを手掛かりに―
|
|
| aa |
1 現実的生起とデカルトの自我 本項と次項では、まず『過程と実在』における現実的生起への言及箇所を分析した上で、それらの箇所の議論が、ローウェル講義から『科学と近代世界』刊行にかけてどのように考えられていたかを確認しておきます。本項と次項では特にデカルトとの関連における現実的生起の記述を分析していくことにします 。ただし、ここでは、ホワイトヘッドの独創的な考えがどのように形成されたかを問題とし、ホワイトヘッドのデカルト解釈の正当性は問題としません。 周知の通り、すべてを疑ってみたデカルトは「第2省察」において、疑っている自我は何ものかでなければならず、「『私は在る、私は存在する』という命題は、私がそれを言い表すたびごとに、あるいは心で把握するたびごとに必然的に真である」という確信に至っています。さらに彼はこのことを確実で揺るぎないものとするべく考察を進め、「私は在る、私は存在する」とは「思考することcogitatio」であり、自我は「考えているものres cogitans」に他ならないという見解に到達した結果、「私は真なるものであり、真に存在するものである」といって、当初の目標であった確固不動のアルキメデスの点を見出しています。 ホワイトヘッドはデカルトに賛同して、主体的経験を離れては無であり、「現実的存在がなければ理由もない」(PR 19)といって、主体的経験を欠く「空虚な現実性」を否定しています。このことは「存在論的原理」とも言い換えられ、あらゆる説明は現実的存在にもとづかなければならないといわれます。ホワイトヘッドによればこの「存在論的原理」は、現実的なものがなければ何もないというアリストテレスの原理を踏襲する原理であり、また、デカルトの『哲学原理』の第I部52節にある文言、すなわち「我々が何らかの属性を知覚するとき、その属性が帰せられる存在するもの、すなわち実体が必ず現前していると我々は結論づける」という文言の基礎にある原理です(PR 40)。ホワイトヘッドの解釈するところ、「考えているもの」であるデカルトの自我は疑いえない「真なるもの」としての実体であり、「デカルトの『実体』という用語は、私[ホワイトヘッド]の『現実的生起』という語句に相当するものなのである」(PR 75)。 無論、ホワイトヘッドはデカルトの説をそのまま継承しているわけではありません。上で言及した「第2省察」の箇所に関して、「『私は在る、私は存在する』という命題は、私がそれを言い表すたびごとに、あるいは心で把握するたびごとに必然的に真である」という確信に至ったあとにデカルトは心的実体が変化を存続すると想定しているとホワイトヘッドは分析し、ここでデカルトは彼の議論を逸脱していると批判します。「というのも、『私は在る、私は存在する』と彼が言い表すたびごとに、自我である現実的生起は異なっているからである」(PR 75)。つまりホワイトヘッドはその都度一回限りの自我を、存続する自我から区別しているのであり、デカルトにおける「二つの自我に共通である『彼』は、永遠的客体であるか、それとも継起する諸生起の結合体である」(PR 75)といって、現実的生起を結合体から区別しています 。 さて、こうした議論は『科学と近代世界』刊行前にもなされていました(SMW Ch. IX, EWM 284, 289, 291)。ローウェル講義に属する「科学と哲学」の章では、「存続しなくなる実体はまた現存しなくもなるから、持続は、思考における場合を除いて、実体より切り離せない」というデカルトの『哲学原理』が引用されます。これについてホワイトヘッドは、心も物体も存続なくしては現存しなくなるがゆえに存続するとデカルトが考えていたと理解しています(SMW 144f.)。ですが、『科学と近代世界』直前のハーヴァード講義4月9日のノートによると、ホワイトヘッドは、自分が前回講義したのと同じ人であるということは驚くべきことであるように思われると語っており(EWM 284)、4月28日のノートには、「デカルトは暗黙裡に、存続する自己を直接的な認識的生起immediate cognitive occasionと同一視している」(EWM 291)と記されています。これらは断片的に書かれているとはいえ、上でみた『過程と実在』の議論と同じ議論だと受け取ってよいでしょう。 本項でみた論点については本節第4項、第5項で再び取り上げることにして、さしあたり本項のことから、ホワイトヘッドはデカルトの「真なるもの」を受け継ぎつつも、存続する自我とその都度異なる自我とを区別したということができます。次項ではさらに主体‐客体図式、知覚の表象理論、主体主義原理の批判に関する議論をみていくことにします。 2 ホワイトヘッドによるデカルト批判 伝統的な実体‐属性図式や主語‐述語形式を鋳直すことはホワイトヘッドが終始一貫して目論んでいた試みでした。この試みは『過程と実在』の「再定式化された主体主義」に結実しています。本項ではこのホワイトヘッド独自の立場をデカルト批判の観点から分析します。 「再定式化された主体主義」の要諦は、「経験の活動における与件が純粋に普遍によって十全に分析されうる」(PR 157)という主体主義原理、別言すれば、個体がまったく普遍だけからなっているということを斥ける点にあります。ホワイトヘッドの解するところ、「第2省察」における蜜蝋の議論 において、当の「自我」であるデカルト自身は一つの特殊であり、諸々の普遍によってのみ性格づけられると想定されています。ホワイトヘッドはデカルトの蜜蝋の議論を知覚の表象理論として特徴づけ、知覚の表象理論を採用しているデカルトの哲学においては特殊な現実的存在の知覚がないといいます(PR 48f.)。つまり、知覚の表象理論では、経験は特殊なるものではなく普遍のみを顕わにするのであって、あらゆる経験が現前的直接性の様態における感覚知覚になってしまいます。その結果、デカルトは、普遍が特殊なるものの諸相を顕わにすると推論することになり、判断の能力によって現実的存在を信じるに至るといいます(PR 49)。ですが、もしデカルトが表象論者として一貫しているのであれば、経験は心に直接現前するものによって尽くされるのでしょうから、つまり経験は単に普遍を顕わにするだけに過ぎないのでしょうから、その推論は決して妥当なものとはなりえず、この考えが一貫しているとするとヒュームの懐疑論に帰着してしまうというのです。 独特なデカルト解釈の正当性はともかく、ホワイトヘッドはこのようにデカルトの蜜蝋議論を分析した上で、ここでデカルトは「想念的実在性realitas objectiva」を導入し、神の力と善性の確信によって有効にされる「判断judicium」を含む知覚の表象理論によって懐疑論を避けていると論じます 。想念的実在性とは、事物が関係性の中で他の事物において表現されている限りでの実在性のことであり、事物がそれ自体においてもっている形相的実在とは区別されます。この議論は表象理論を逸脱しデカルトの哲学と矛盾するものなのですが、「有機体の哲学」は想念的実在性という説を採用し、それを整合的な存在論によって解釈しようと試みます(PR 49)。すなわち、現前的直接性の様態とともに因果的効果の様態の知覚も経験の一部分とすることによって、単なる普遍ではない現実的存在の抱握を認めるのです。 さて、同様のことはローウェル講義でも議論されていました。周知の通り、デカルトは物体と心を実体とし、空間的延長を物体の属性、思考を心の属性としました。ホワイトヘッドの思想史理解では、デカルト以後、科学は、時間や空間内に単に位置を占め、法則にしたがって運動する空間的物体からなる客観的世界を主題とし、哲学は、色や音、匂い、味、感触、身体的感覚といった心の主観的内容からなる主観的世界を主題としました。かくして近代は二元的な図式を前提することになりました。ですが、後者について、例えば色は結局のところ心のうちにおかれ、心は私的な思考世界に局限されることになるのであり、「経験における主観客観の完全な合致は、心だけの私的な受動的働きの一つとして心のうちにある」(SMW 146)ことになります。ホワイトヘッドはこの点について、蜜蝋の知覚は「単に心の直観である」という「第2省察」の箇所を引用して、デカルトは思考する心の観想theoryによって客観的物体が知覚されると考えたと解釈しています(SMW 146)。 しかしこれに続く箇所では、19世紀末における心理学に対する生理学の影響を引き合いに出しながら、デカルトの考えは暗に否定されています(SMW 147ff.)。すなわちホワイトヘッドは、人間の身体を考察するときに物理学者の態度で臨んだデカルトではなく、ジェイムズなど生理学的素養も併せもった心理学者たちに同調し、外的事物の知覚において知覚者の身体の諸相の集まりが知覚者当人に示されると考えています。身体的出来事も含めて自然内の出来事においては、それらの諸相が相互に映されることによって本質的に影響しあっているのであり、認識は、身体の介在も含む有機的な連関全体の統一体として成立します。「有機体の哲学」の根本的原理は、「融合して現実となるものはすべて自らの諸相をあらゆる個々の出来事に植えつけるということ」(SMW 150)であり、知覚者当人がもっている感覚的客体の諸相は外的事物の認識に影響していると考えられるのです 。 この議論においては外的事物の認識が間接的推論に依らねばならないことは否定され、むしろ想念的実在性というかたちで外的事物は直接的に直観されるという主張が読み取れます。実際、ローウェル講義に属する「18世紀」の章の注ではデカルトの「『省察』に対する諸異論への応答」の一節に同意していることから、想念的実在性の着想はこの時期にありました。その一節とは、「太陽の観念は、太陽が空に存在するが如く形相的にではなくとも、諸対象が常に心のうちに存在するような仕方で客観的に、心のうちに存在している太陽そのものなのであろう」(SMW 73f.; cf. PR 76)という一節であり、『過程と実在』の議論の原型はローウェル講義にも見出せます。 本項では、ローウェル講義時でも既にホワイトヘッドは、主体主義原理を批判しつつも、デカルトにおいて整合的ではなく導入されている想念的実在性を採用し、間接的推論に依らない外的事物の直接的直観を認めようとしていることを明確にしました。ホワイトヘッドによれば、特にこのようにデカルトを悪しき方向に惑わしてきたのはアリストテレス以来の主語‐述語形式です(PR 49)。主客の区別は主語‐述語形式の名残を含み、諸客体の下にある一つの基礎的存在を指し示しますが、このような客体という考えはアリストテレスの述語の亡霊に過ぎません(SMW 151)。では、ホワイトヘッドはどのように伝統的な枠組みを超克して、自らの立場を打ち立てていったのでしょうか。次項以下でこの点を明らかにしていきましょう。 3 ジェイムズとホワイトヘッド 『過程と実在』第II部でホワイトヘッドはデカルトに言及したあと、近代哲学は、主語‐述語、実体‐属性、特殊‐普遍によって世界を記述するという困難を抱え、その結果、直接経験を歪めてきたと非難します。注目すべきは、その直後に、「我々は、被造物同士の民主主義の唯中で、ざわつく世界のうちに見出される」(PR 50)というジェイムズの言葉を引用していることです。こうした伝統的な枠組みへの不満とジェイムズへの賛辞はローウェル講義に属する「科学と哲学」の章にも見出され、そこでは、近代哲学の口火を切ったデカルトの『方法序説』に、ジェイムズの「『意識』は存在するか」(1904年)が対照されています(SMW 143ff.)。ホワイトヘッドは自説に引きつけながら、ジェイムズはデカルトの主張を否定していると解釈し、それに概ね賛同しています。そうであるなら前項のデカルトの問題点を超克するすべをジェイムズから見出すことは、ホワイトヘッドの思索と重なるところがあるでしょう。本項では、ホワイトヘッドの言及を参照しながら、次項の議論に必要となる限りでジェイムズの哲学を概観しておきます。 「『意識』は存在するか」でジェイムズは、哲学の伝統に蔓延ってきた認識者‐認識対象、主観‐客観、心‐物質といった種々の形態の二元論を批判します。特に意識についてジェイムズは「その言葉が何らかの存在entityを表している」ことを否定し、「その言葉はある機能を表している」と主張しています 。内容のない意識そのものは存在せず、「物質的事物を構成する素材と対比される意味で、それら事物についての我々の思考を作っているとされる原初的な素材とか存在の質というものは存在しない」 というのです。 ホワイトヘッドは、存在や素材でジェイムズの意味することが曖昧であり、存在という概念は極めて一般的であるから、考えられるどんなものをも意味すると受け取ってよいだろうという批判はしています。すなわち、のちに「存在論的原理」として表明されるように、「我々は全くの無について考えることはできないのであり、思考の対象となるものは存在と呼ばれてよいだろう」といい、「この意味で機能は一つの存在である」という批判はしています(SMW 144)。しかし、ホワイトヘッドの賞賛するところ、存在と機能の区別こそジェイムズの革新的な挑戦でした。 ジェイムズは、先行する新カント派の思想家たちが、二元的な内的構成をもった経験から分析によって意識を析出できる、つまり「経験内容の方を抽象すれば、意識の方が浮かび上がってくる」 と想定していることを批判した上で、中立的な「純粋経験pure experience」から意識と内容を説明します。絵の具から溶剤や顔料をそれぞれ抽出するが如く「引き算」によって経験を意識と内容に分離することはできないのであって、反対にジェイムズは、「経験が意識と内容に分離されるのは引き算によってではなく足し算によってである」と主張します 。つまり、「ある与えられた未分離な経験の一片が、ある連合の脈絡では、認識者や、心の状態、『意識』の役割を演じ、別の脈絡では同じ未分離な経験の一片が、認識されるもの、客観的な『内容』の役割を演じるということである」 。未分離な経験の一片は脈絡によって思考として現れたり物として現れたりするのであり、主観的・客観的という規定性は脈絡において初めて機能します。 ここで、「ある与えられた未分離な経験の一片」とは純粋経験に他ならないのですが、「それが何であるかを決定するまでは単なるあれでしかない」 。回顧的経験も含め、純粋経験は「現在の瞬間的な領野」であり 、「それは制約づけられていない素朴な現実性ないし現存であり、単なるあれである」 。「あれ」である純粋経験が、例えば、部屋で本を読んでいる読者の個人的な歴史である過程の成員となったり、その部屋を部分とする家の歴史である過程の成員となったりします。純粋経験それ自体は物的でもなければ心的でもなく、如何なる脈絡におかれるかによって物的な機能を果たしたり心的な機能を果たしたりするというのです。 『過程と実在』におけるホワイトヘッドの現実的存在あるいは現実的生起も単独では何ものでもなく、「足し算」によって決まるわけではないとはいえ、他の現実的存在との関係の中で地位statusが決定するとき、それが物的に機能するか心的に機能するか決まっています 。機能するとは「ある現実的世界の結合体内にある現実的諸存在に決定を与えること」であり、「決定」には「現実的諸存在からなる結合体における相対的地位」の確定が含まれています(PR 25)。しかも、ある現実的存在の機能が現実的諸存在の内的関係の中で決まるとはいえ、関係性を普遍とみなすブラッドレーに対してホワイトヘッドは、経験されるものや経験の働きはどれも全宇宙を包含する特殊なる過程であって、「あれ」という「指示的要素demonstrative element」であると考えていることも付言しておこう(cf. PR 43, 200, 229)。 とりわけ純粋経験と意識の問題は特異です。ジェイムズの純粋経験は、脈絡に位置づけられるまではただ「あれ」というほかない直接経験であり、それ以上遡って問うことができない実在とされます 。この意味で純粋経験はカントの統覚を転倒させた位置づけを有し、カントの「私は思考する」とジェイムズの純粋経験は認識論的な一つの原点として類似しているといえなくもありません。にもかかわらず、超越論的に要請される統覚に対して、純粋経験は直接的事実として与えられるという強みをもちます。「『意識』は存在するか」の最後でジェイムズは、「私のすべての対象に伴いうるのでなければならないとカントがいった『私は思考する』とは、すべての対象に実際に伴っている『私は呼吸する』のことである」 といいます。『心理学原理』でも自我は超越論的主観ではなく、“it thinks”とでもいうべき「思考の流れ」に過ぎないとされていました。ジェイムズによれば意識の原初的事実は思考が流れているという主観でも客観でもない感受feelingです。感受は、主と客、自我と対象の分離以前のものであり、誰のものとか何であるといった規定をすることができません。 もちろんジェイムズも「経験の中にあって思考が果たす機能」、すなわち「知る働きknowing」を認めており、「『意識』は、事物が単にあるだけでなく報知されるすなわち知られるという事実を説明するために必要だと想定される」と考えています 。ただし、ここで知る働きとは一種の関係であり「この関係自体が純粋経験の一部分である」 。そして「その関係し合う『諸項』の一方が認識主観あるいは認識の所有者、知るものthe knowerとなり、他方が認識される対象となるのである」 。ジェイムズの哲学にあっては、自我がまず存在して何かを経験したり知ったりするのではなく、知る主体もその対象も、未分離な経験から機能的に生じてくることになります 。 両哲学における感受の比較に深入りするのは避けますが、積極的抱握である感受という発想にはジェイムズからの少なからぬ影響があったと推察されます。『観念の冒険』の第15章第11節においてホワイトヘッドは、積極的抱握である感受という用語がブラッドレーの用いる感受と類似していることを述べた上で、「ジェイムズもまた彼の心理学において、この語をほとんど同じ意味で用いている」(AI 231)と付言し、『心理学原理』の次の箇所を引用しています 。
ホワイトヘッドがジェイムズから多くを負っているのは自身で認める通りですが、発展史研究の観点からは、どのような仕方でジェイムズの哲学を受容していったか、特に『科学と近代世界』の形而上学成立期においてどのようにしてのちの形而上学で展開されるような仕方で意識や認識を論じるようになっていったのか、といったことが興味ある論点です。次項ではこの点についてみていくことにしましょう。 4 ハーヴァード講義における意識 ジェイムズと同様、ホワイトヘッドもローウェル講義の「科学と哲学」の章で「意識とは知る機能であろう」(SMW 151)といいます。さらに主体‐客体、主語‐述語といった伝統的な枠組みを批判したあとでは次のように述べています。 認識経験に現れる原初的境遇は「諸客体間にある自我としての客体ego-object」である。すなわち、原本的事実は、自我としての客体的存在を示す「今ここ」を超越し、かつ一切を同時に実現させている空間的世界である「今」を超越する、いずれにも偏らない世界である。それはまた、過去の現実性と、限られた未来の可能性とを含む世界であり、抽象的な可能性の世界全体complete world、すなわち現実的な実現の過程actual course of realisationを超越し、しかもその過程内で例証を見出しその過程と対比される永遠的客体の領域を含む世界である。今ここにおける意識としての自我としての客体は、自己の経験的本質が実在界と観念界とに内的に関係することから成り立つことを意識する。しかしこのように成り立つ自我としての客体は実在の世界のうちにあり、このように諸々の実在における地位をもつために観念が進入することを必要とする一つの有機体として自らを示す。だが、この意識の問題を扱うことは他の機会に譲らなければならない。(SMW 151f.) 『科学と近代世界』刊行時に加筆された箇所でも意識について明示的に論じられていないのですが、ハーヴァード講義では意識について論じられていました。本項では、ローウェル講義からハーヴァード講義にかけての思索を跡づけます。 ローウェル講義でホワイトヘッドはデカルトの『方法序説』と『省察』に言及し、デカルトは経験を受け取る主観、すなわち心である当のデカルト自身から出発しているのですが、「この心は、心自身に内在する感覚および思考の表象を意識することによって自身の存在を統一的存在として意識している」と述べています(SMW 141)。前節の最後で触れた通り、ローウェル講義で、反省を含むような認識や対自的自己関係は出来事のうちに見出されていました。注目すべきは、ローウェル講義と連続してハーヴァード講義4月9日にもホワイトヘッドは、「認識は自己認識self-cognitionである」と述べた上で、「出来事が対自的に何であるか」こそが『省察』の主題であったとデカルトに言及していることです(EWM 283)。 そのノートには「デカルトの認識は彼自身以外のものの『直観inspectio』を含む」と記されたあと、「彼が何であるかを問うときに彼が見出す最初のことは、実体と属性という考えが当てはまらないということである。認識されたものcogitataは心の性質として表象されえない」と書かれています(EWM 283)。ホワイトヘッドの解釈にしたがえば、デカルトの哲学で外的事物はあくまでも心の表象に過ぎないはずですが、ここでもホワイトヘッドは、認識対象は私的な心の表象ではありえないと批判し、外的事物の直観を主張しています。 こう主張する際、ホワイトヘッドは、自我を諸事物の相互関係のうちに解体しようとしていたようです。
この箇所は、諸々の普遍を通してのみ世界と関わる孤立的なデカルトの自我を斥け、相互に影響しあう諸事物の内的関係のうちで自己意識あるいは自己認識を捉え直そうとしていたことを示しています。 しかもそのとき、他の諸事物との関係のうちに解体される限りで、自我は他の諸事物と同等の存在論的身分へといったん格下げされます。4月16日のノートには、生理学に裏付けられた現代心理学は主観‐客観という見方が相応しくないことを示しており、自我は諸客体の中の一つであって「諸客体間の私I-amid-objects」であると記されています(EWM 287)。デカルトにおいて「私」は「考えているもの」であり、その限りで「私は存在する」といわれましたが、のちに『過程と実在』で「我々は、我々が存在するのと同じ意味で諸現実態からなる世界に存在する他の諸事物を知覚する」(PR 158)と述べられているのと同様、ここでホワイトヘッドは自我を諸客体のうちの一つとみなしているのです。特に、断片的にではありますが同日のノートには「下にある主体は間違っているSubject―lying under―wrong」と記されています。そうであれば、諸事物が共に構成している内的internal関係とは、それ自体で存在する実体的主体の孤立性を支える内的関係ではなく、相互関係における本質の依存という意味での内的関係でしょう。 ここで、主体‐客体図式や主語‐述語形式、それにもとづいたデカルト哲学を批判する材料として挙げられている、生理学と結びついた心理学には、前項で参照したジェイムズの心理学研究が含まれているでしょう。デカルト哲学の場合、外的事物は心の表象に過ぎませんが、ホワイトヘッドはジェイムズの主客分離以前の感受に賛同して、デカルトの直観を外的なものの直接的直観(=積極的抱握である感受)へと解釈しなおしたと考えられます 。 反省を伴う認識や意識は、こうして自我を諸事物の内的関係の中へいったん解体した上で捉え直されます 。4月18日のノートでは、「自我としての客体が諸客体からなる世界のうちに」あり、「諸客体からなる世界は、その世界における各客体の本質を修正する」と記されています(EWM 289)。そしてさらに、「自我としての客体は他の諸客体のうちで自らを知る」と書かれています(EWM 289)。この「自我としての客体」とは中期哲学における「知覚しつつある客体」に相当し、ローウェル講義では認識経験や主体性をもつ高度に組織された複雑な有機体と同等視されていましたが、今や「自我としての客体」が自らを知るという問題が主題化されているのです。 続く4月28日のノートによれば、心という素材という考えに異議を唱えデカルトと完全に見解を異にしているジェイムズの「『意識』は存在するか」に、ホワイトヘッドは完全に賛同しています(EWM 290)。そうであれば、ジェイムズと同様にホワイトヘッドも、対象から分離した知る主体、あるいは内容のない意識そのものを最初に措定しているわけではないでしょう。むしろ完全に賛同していたのであれば、未分離な経験の一片たちの関係として意識の機能的成立を論じようとしていたのではないでしょうか。 では、どのようにホワイトヘッドは自らの哲学体系内に意識を位置づけたのでしょうか。同日のノートには、唐突ながら「意識とは、創発する存在emergent entityと、その存在がそこから創発するところの構成的可能態との間の関係である」(EWM 291)と定義されています 。本項冒頭で引用した通りローウェル講義では、「自我としての客体」を含む実在界と観念界とが内的に関係することから意識は成立すると考えられていましたが 、想念的実在性から着想される物的感受が認められても、直観された所与が単に概念的に再産出されるだけならそこに意識は見出されません 。むしろ上の定義は、様々な可能態が観念的にはありうる中で、それら可能態と、現にある所与とに対比的な関係が生じるところに意識が見出されることを主張しています。 ホワイトヘッドがこのように意識を定義したのは、関係における機能を論じたジェイムズの影響とともに、意識の成立には誤る可能性が不可欠と考えていたからだと推測されます。『過程と実在』で意識が「誤っているかもしれない『理論』と、『所与の』事実とのコントラストを感受するときに含まれる主体的形式」(PR 161; cf. PR 261, 267)と定義されるのに先立って、5月7日のノートでは、ベルグソンは直観を賛美して誤りが思考とともに始まると想定する傾向にあったこと、「人は考え始めるとき間違って考える」ということ、自己意識とともに誤りは重要度を増すことなどが記されています(EWM 294)。意識は、別の可能的な選択肢と事実とのコントラストが感受されることをその本性とする限りで、誤りと表裏一体であると考えられていたのです。 しかし注目すべきは、ここでホワイトヘッドがそもそも直観は誤りのないものなのかどうかに疑問を呈している点です。同日のノートには、動物の行動が無分別ill-judgedであり、「長い目でみれば、意識は誤りを避けることを可能にする仕方である」(EWM 294)と記されています。意識はただ単に事実と別の可能態とのコントラストを感受する仕方であるに尽きず、価値の重要性に応じて選択する実践にも結びついています。『教育の目的』や『理性の機能』、『観念の冒険』で説かれるように理論理性と実践理性は分離されうるものではなく、「ケーラーは、サルが障害を乗り越える能力によって思考の現前を判断していた」(EWM 294)とも記されていることから、意識は、人間ほど高次でないその原初的形態から、うまく生きること、より善く生きることをその本性とする生命の技巧artとして捉えられていたのでしょう。 以上のことは、ホワイトヘッドが、誤るかもしれないところに意識の成立を見出すとともに、それでもやはり理性的な意識や知に対して信頼を寄せていたことを物語っています。「有機体の哲学」が「純粋感受批判」を構築しようとしていたことはよく知られていますが(PR 113)、ハーヴァード講義でも既に「カントは3つの批判書をまとめるべきだった」(EWM 288)と考えられ、ホワイトヘッドは、主客の対立や感性‐悟性‐理性の区別が生じる以前の原初的経験である感受から、意識の成立を論じるとともに、それを実践と結びつけようとしていました。ホワイトヘッドは実践哲学の著作を書かなかったともしばしば指摘されますが、その哲学全体は、理論と実践という区別が生じる以前の原初的経験にまで遡った上で実践哲学への展開を孕んでいる哲学なのです。 本項では、ローウェル講義からハーヴァード講義にかけてホワイトヘッドがどのように意識を考えていたかを跡づけてきました。伝統的な主体‐客体図式は内的関係の説に取って代わられ、ホワイトヘッドは、ジェイムズへの賛同のもと、知る主体を最初に措定するのではなくむしろ主客の対立が生じる以前の原初的経験から意識の成立を論じていたのです。如何にしてホワイトヘッドが伝統的な主体‐客体図式を鋳直し、特に近代の主体概念に密接に関わる意識的自我を自身の体系で論じていったかを問うとき、まさに本項で追ってきた議論は、諸客体の下にあるものとしての主体を否定し、むしろ諸客体から如何にして主体が生じてくるのかを論じるものでした。 実は、このことは、「有機体の哲学」における最も基本的で独創的な考えだとされる、現実的存在(現実的生起)や結合体の発想の起源にも関わっていると思われます。現実的存在actual entityや結合体nexusという言葉自体は、『科学と近代世界』ではまだ登場しないのですが、現実的生起actual occasionという用語は、『科学と近代世界』の付加された箇所で使われています 。この生起という言葉は、ハーヴァード講義で頻繁に使われるようになっています 。それと同時に、上述の、諸事物が内的に関係づけられた共同体は、『過程と実在』における結合体の萌芽だと考えられます。次項では、この点を検討します。 5 現実的生起とその共同体 第3節の最後で触れた通り、ローウェル講義で、「心的認識は、ある全体の反省的経験であって、一つの統一的現象としてそれが自体的に何であるかを自らに対して報知するものとみられる」(SMW 148)と述べられていましたが、心的認識は、出来事、それも人間のような複雑な有機体の出来事についてだけ語られていました。ハーヴァード講義4月9日のノートでも、「出来事が対自的に何であるか」こそが『省察』の主題であったとデカルトに言及しているとき、対自的自己関係は出来事という概念のうちにみられていました(EWM 283)。 しかし、前項でみた通り、4月28日にはホワイトヘッドは、諸客体の下にあるものとしての主体概念を否定し、知る主体を最初に措定するのではなく、むしろ主客の対立が生じる以前の原初的経験から意識が成立すると考えるに至っていました。再度引用しておくならば、「意識とは、創発する存在と、その存在がそこから創発するところの構成的可能態との間の関係である」(EWM 291)と定義されていたのです。注目すべきことに、同日のノートでは、意識がこのように定義されたのち、後期ホワイトヘッド独自の術語である「生起occasion」という言葉が多用されています。本節第1項でみたようにデカルトの「真なるもの」に取って代わるのが現実的生起であり、ホワイトヘッドはデカルトの哲学を批判的に受容することを通して独自の見解を形成していったとすれば、(現実的)生起および結合体の発想は、意識的な自我および近代における主体概念の解体に何らかの点で関与していたのではないでしょうか。 4月28日のノートでは、上のように意識が定義されたすぐあとに、実在論と観念論が対立する問題について論及されています。それによると、意識が上のように定義されると、認識はそれより下位の存在、つまり所与の事実を前提し、「認識を含む生起occasion inclusive of c[ognizance]は、認識を含まない同じ事実the same facts exclusive of cognizanceを前提する」 (EWM 291)と記されています。これはどういうことでしょうか。 前節でみた通り、知覚は認識的把握であり、意識を含意していました。しかも抱握は非認識的把握であり(SMW 69)、「知覚は抱握の認識である」(SMW 71)のですから、抱握的統一化は、意識を含意する知覚や認識的把握とは独立に実在的でした。「暫定的実在論」の立場をとるホワイトヘッドにとって、身体的出来事や自然内の出来事は、それ自体、統一体なのであって、知覚者がそれを意識的に認識するか否かにかかわらず、実在的な事実です。それら実在的な事実は、想念的実在性というかたちで、直接的に直観されます。 しかし意識は、単に事物を直接的に直観することによっては成立しません。ローウェル講義から言われているように、「今ここにおける意識としての自我としての客体は、自己の経験的本質が実在界と観念界とに内的に関係することから成り立つことを意識する」(SMW 151f.)。つまり、意識は、事物の直接的直観と、様々な観念とのコントラストが生じるときに成立するのです。意識を伴う認識はこのときに問題になるだとすれば、事実は、観念や意識の有無にかかわらずそれとして実在してもよいでしょう。換言すれば、上のように意識が定義されるならば、認識は、それ自体で統一体である身体的出来事や自然内の出来事の(認識とは独立の)実在性を認める余地を残します。むしろ、認識は、認識とは独立に実在する所与の事実を前提しなければなりません。つまり、ここで、認識が事実そのものを変えるわけではないと認められる限り、実在論と観念論は両立することになります 。このことは「認識の半透明性translucence of cognizance」と呼ばれ、「抽象」の章では「実現の半透明性の原理」として採用されることになります 。 先の一文をこのように理解すると、“cognizance”は、必ずしも人間的な意味での反省的意識を伴うわけではないと思われます。“recognition”や前項で言及した“cognition”が反省的なものを含みその限りで「再認」とか「認識」と訳しうるのに対して、ここでの“cognizance”は、むしろ反省を含まない認識という意味で「認知」を意味しているでしょう。以下、“cognizance”を「認知」と訳します。 さて、生起という術語は、こうした認知としての“cognizance”の理解とともに導入されました。出来事という概念は、特に人間などの高度に複雑な有機体の場合、反省的な自己認識や対自的自己関係を含意していました。そうであれば、例えば反省的な自己認識が発生論的にどのように成立するかを、出来事という概念によって分析したり記述したりすることはできないでしょう。確かに、粗野な経験を指す出来事によって、反省を含むような複雑な経験を指す出来事を説明することもできるでしょうが、その場合、後者の出来事は、前者の出来事によって構成されることになります。粗野な経験を指す出来事も、複雑な経験を指す出来事も、それぞれ一つの統一的な出来事であるにしても、この意味において、粗野な経験を指す出来事は、複雑な経験を指す出来事よりも基礎的です。生起という術語は、前者のような出来事に取って代わる概念として案出されたと推察できます。つまり、生起は、主語‐述語形式や主体‐客体図式といった粗い概念では不可能であった、複雑な経験の発生論的分析を可能ならしめる術語です。 このことは存続という特性と対比してみるとわかりやすくなるでしょう。ホワイトヘッドは認識の半透明性を論じる際、「立脚点となる生起の自己self of standpoint occasions」と「認知する生起の自己self of cognizant occasions」とを区別しています 。認識の半透明性の議論と並行する区別が、存続する存在にもなされうると書かれたあとで、「認知する自己cognizant selfはどんな生起の本質の分析においても断続的で移ろいやすい」のに対して、「立脚点となる生起の自己」は存続に関わり、「経験しつつある自己experient self」とも言い換えられています(EWM 291)。 ローウェル講義で出来事は、「それ自身に含まれる経歴を伴った存続する個体的存在という姿で実現される」(SMW 104)とされ、パターンの反復という仕方で存続を含意する有機体でした。「具体的な存続する存在は有機体である」(SMW 79)とも言われていた通り、出来事はここでいう「立脚点となる生起の自己」および「経験しつつある自己」の役割も担っていました。 しかし、「立脚点となる生起の自己」や「経験しつつある自己」とは異なり、「認知する生起は、認知する自己の直接的知識を構成する直接的イメージである」(EWM 291, cf. PR 160f.)。ジェイムズの純粋経験が現在の瞬間的領野において生起するが如く、認知する生起は、第一義的には、直接的現在にのみ関わるということでしょう。存続する自己の方は、昨日も今日も同じであるといえるような自己であるのに対して、認知する自己の方は、その瞬間ごとの自己であり、「眠っていたり起きていたり、多くの認知する自己が存在する」(EWM 291)。 出来事という概念には、経歴をもち存続する出来事と、直接的で一回限りの出来事の二義性がありましたが、「立脚点となる生起の自己」と「認知する生起の自己」はその二義性を区別します。ローウェル講義では、私的心理領域はそれ自身の立脚点から考察された出来事に過ぎず、この領域の統一性が一つの存在としての出来事の統一性であるとされた(SMW 150)。これに対し、生起は、出来事の統一化の過程を発生論的に分析するのに、出来事よりも基礎的な概念といえるでしょう。 特にこの区別は、私的心理領域をもつデカルトの実体的な心を鋳直す中で浮上してきたのであり、本節第1項で分析した通りデカルトにとって主体であった実体としての自我(=結合体)は「立脚点となる生起の自己」に当たり、「私は在る、私は存在する」とデカルトが言い表すたびごとに異なっている自我(=現実的生起)は、直接的現在に関わる「認知する生起」ないし「認知する生起の自己」に相当するでしょう。のちに、「時間」という小論(1926年9月)の一節でも、「『存続』をその重要な属性の一つとしてもつデカルトの実体の代わりに、我々は『継起supersession』をその実在的本質の部分としてもつ一つの『生起』という概念を設定しなければならない」(EWM 303)と述べられており、こうした現実的生起の由来を示唆しています 。 また、以上のようなハーヴァード講義の議論は、ローウェル講義におけるライプニッツ批判とも関連していると思われます。すなわち、ホワイトヘッドが批判するところ、ライプニッツのモナド論は、内的関係を許容する、「諸成分を一つの統一体へと融合し、その結果この統一体が実在となるような、有機体化する活動力」と、内的関係と相容れない「諸性質を備えた実体」という2つの考えのうちに困難を抱えています(SMW 155)。これに対してホワイトヘッドは、ハーヴァード講義で、経験する実体的主体を措定することなく諸事物の内的関係から出発し、「如何なる実在する主体も、内的関係性の共同体communityを構成している他の諸事物のうちの一つである」(EWM 283)と考えるのでした。同じ箇所では、「そのものが何であるかを問うとき、他の実在物が何であるかを考慮することを避けることはできない」(EWM 283)と記されていた通り、内的に関係づけられた諸事物は本質において依存しており、想念的実在性という発想を取り入れることによって、それぞれの生起は、意識をもつか否かにかかわらず、他の生起に表現されていることになるでしょう。諸生起が相互に表現しあい、内的に関係するこの共同体こそ、『過程と実在』の結合体の前身に相当すると考えられます。強いて言えば、実体は、この結合体に相当するのですが、ホワイトヘッドは諸々の属性をもつ基体的実体に批判的なのですから、あくまでも結合体は、諸生起の共同体として構成されるものだと理解されなければなりません。ホワイトヘッドは、モナドから実体という身分を剥奪し、諸生起を有機体化する活動力と、諸生起の内的関係を許容する共同体(=結合体)を両立させようとしたのでしょう。 さらに、本章の第3節の最後で触れたように、ローウェル講義では、ライプニッツは「経験の単位としての出来事」を、「存続的有機体」や「個体化の成長した完全性を表している認識的有機体」と区別しなかったとも批判されていました。ハーヴァード講義の議論からすれば、存続的有機体は、諸生起から構成される共同体であり、特に認識を含むような存続的有機体が認識的有機体でしょう。ライプニッツにとってモナドは、認識を含むものも含まないものもモナドであったように、ローウェル講義の出来事も、認識を含むものも含まないものも出来事と呼ばれていました。認識を含む出来事も単に自然的な出来事もすべて、経験の単位としての出来事なのです。ローウェル講義において、ライプニッツに対するホワイトヘッドの批判点は、そのような経験の単位としての出来事(=生起)と、そのような出来事から構成された共同体(=結合体)として考えられる限りの出来事とを区別しなかったことにあります。つまり、既述の通り、出来事という概念には二義性があります。しかし、生起とその共同体が概念的に区別されれば、出来事の二義性が概念的に区別されます。『過程と実在』では、生起は経験の単位としての出来事を意味し、結合体は、有機的に内的に関係づけられた共同体としての出来事を意味するようになっていると考えられます 。逆に、この二義性の名残として、『過程と実在』で出来事は、歴史的経路をもつ諸々の現実的生起の結合体と定義される一方で、現実的生起は、要素がただ一つだけであるような限定された類型の出来事であるとも定義されています(PR 73, 80)。 以上みてきた通り、ホワイトヘッドは、自身の哲学において意識や主体を論じ直していく中で現実的生起や結合体の発想に辿りついたと考えられます。現実的生起は、第一義的には、現在における瞬間ごとの経験であり、それら諸生起は内的に関係づけられることによって共同体を織り成します。それが、『過程と実在』における結合体という発想の起源でしょう。伝統的な主体概念や、近代における意識的な自我は、ホワイトヘッドの哲学にとっては、現実的生起や結合体によって説明されるべき派生物となります。むしろ諸事物はその本質について互いに依存しており、ある事物が何であるかは、他の諸事物との関係を抜きには規定されません。逆にいえば、どの事物も、他の諸事物の何であるかを規定するようなものとして存在します。あらゆる存在が主体であるという説はこの意味で理解されるのであり、その着想は、中期哲学からハーヴァード講義にかけて形成されていったのです。 |