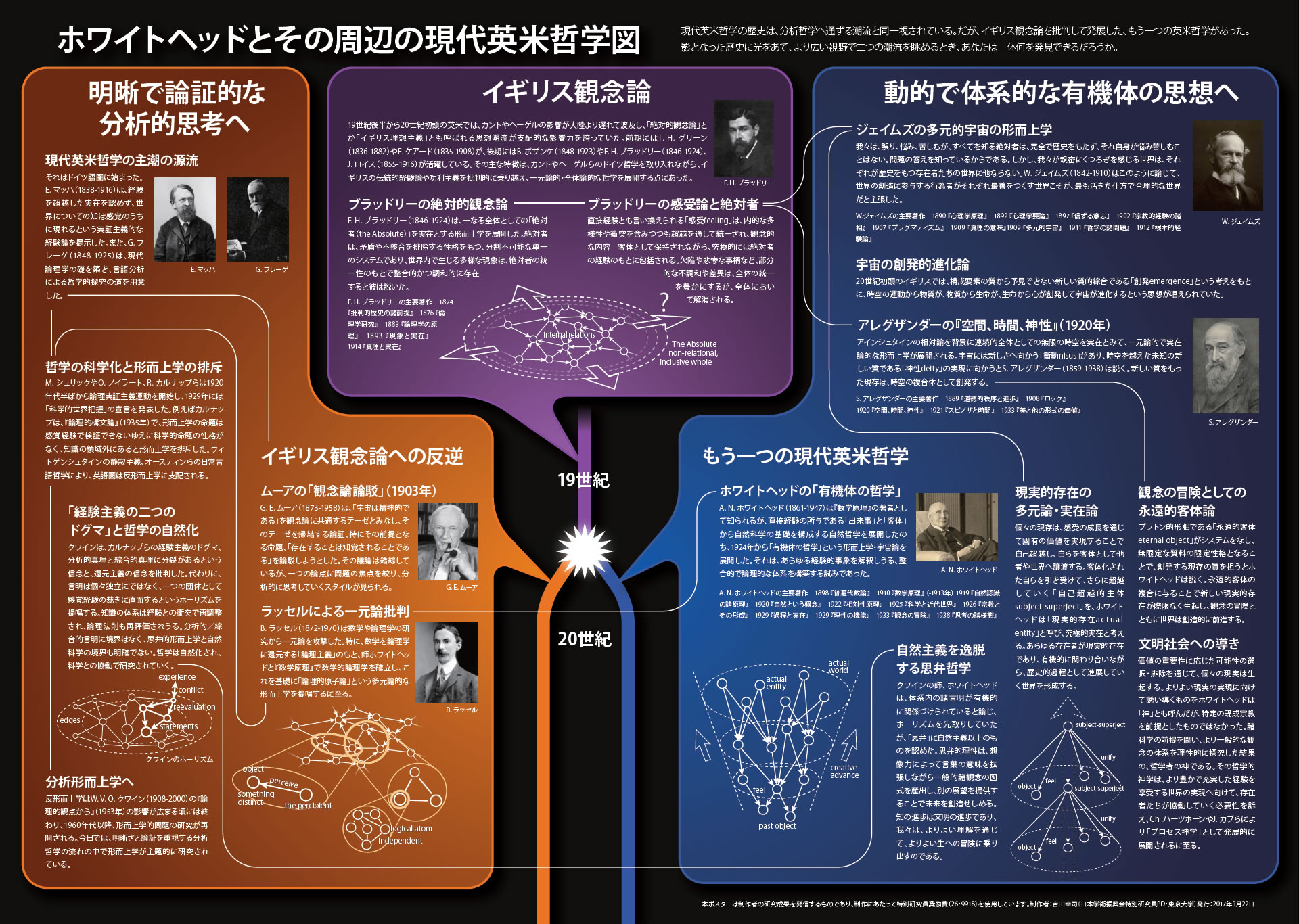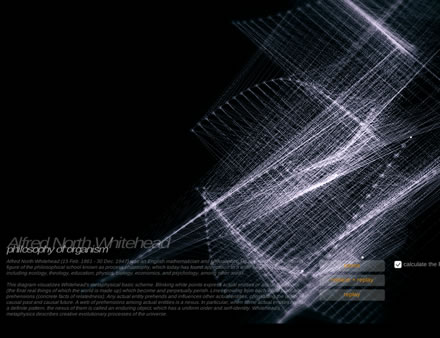現実的生起・抱握・結合体の発展史的起源
aaa
|
ホワイトヘッド哲学の基本的諸概念と主体
|
|
| aa |
「有機体の哲学」に特徴的な主張として、あらゆる存在が主体であることがしばしば強調されます。「有機体の哲学」によれば、原子や分子といった無機物から人間に至るまで、どんな瑣末な存在も主体であり、このことは、のちの研究者によって「汎主体主義pansubjectivism」(フォード)とか「汎経験主義panexperientialism」(グリフィン)とも呼ばれます。
しかし、原子や分子が主体であるといっても、無論、それらが意識をもつことを主張するわけではありません。そもそもホワイトヘッドは、伝統的な哲学において容認されてきた主体subjectという概念に批判的であったし、すべての存在が主体であると最初から考えていたわけでもありません。後期哲学で主体性は、個々の現存が自己実現していくまさにその働きとして理解されますが、中期哲学では、そのような考えが少なくとも体系的に展開されてはいませんでした。後期哲学とは異なり中期哲学では、現実的存在・現実的生起 という術語が登場していなかったばかりか、自然内で知られるものにその考察対象が制限されていたのです 。次節以降でみるように、主体概念に対する独自の見方は中期にもあったと考えられますが、体系的な記述が与えられていったのは、『科学と近代世界』とそれ以降においてです。 このことは、この時期にホワイトヘッドが自身の哲学体系内において主体(性)を位置づけていったことを暗示しているでしょう。しかも、注目すべきことに、現実的生起という術語は、『科学と近代世界』が刊行される直前に使われるようになっているし、結合体のもととなる考えもそれと同時に見出すことができます。序論でも述べた通り、『過程と実在』によると、究極的な実在である現実的存在は、存在論的原理や抱握、結合体とともに、従来の哲学的思想とは異なる独自の概念であり(PR 18)、「直接的な現実的経験の究極的諸事実は現実的存在、抱握、結合体である」(PR 20)。これらは「有機体の哲学」がそこから出発するところの最も基本的な概念であって、最も具体的であるがゆえに、それら自体を説明することはできません。ですが、そうだとしても、ホワイトヘッドは自身の哲学体系を構築する中でそれらの術語を用いるようになったのだから、如何にしてホワイトヘッドが現実的存在・現実的生起や、抱握、結合体といった術語を案出したのかは説明することができるでしょう。 次節以降では、主体という論点を中心に過渡期ホワイトヘッドの思索を跡づけることによって、神を除く現実的存在、すなわち現実的生起や、抱握、結合体という考えの発展史的起源を明らかにします。まず次節では、経験experienceや主体、および近代における主体概念に密接に関わる心mind(心性mentality)に関する用語上の区別とその分析をしておきます。その上で、ローウェル講義においてそれらがどのように考えられていたのかを跡づけます。その後、1925年ハーヴァード講義から『科学と近代世界』の刊行に至るまでのホワイトヘッドの思索を跡づけていきます。 |